Startale Japan ブロックチェーンインサイト10月号
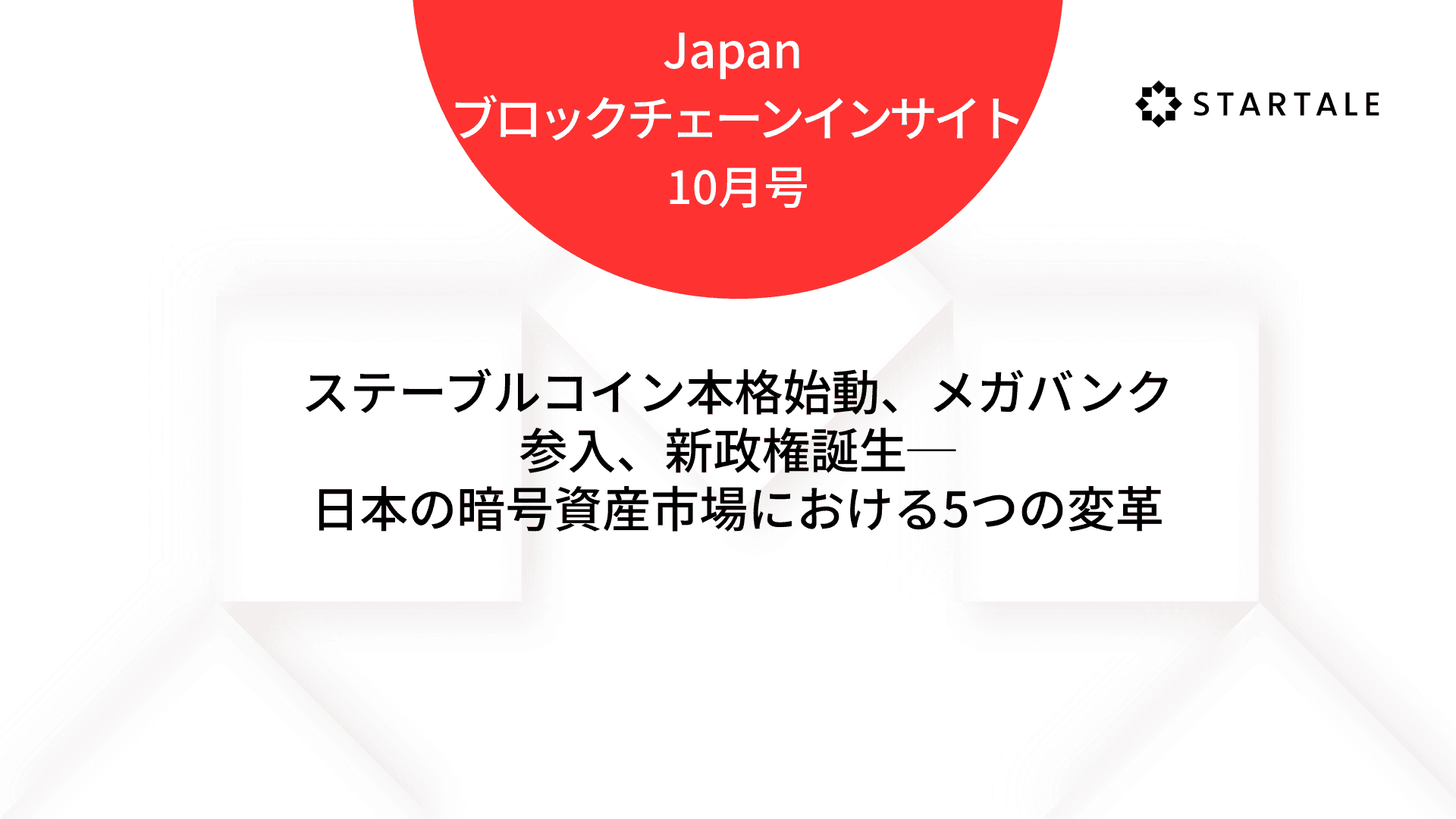
はじめに
本レポートは、日本のブロックチェーン業界における主要な動向を定期的に整理し、業界の理解促進を目的とした定期レポートです。今回が初回となる2025年10月号では、ステーブルコインの本格始動、決済と暗号資産の融合、金融インフラの進化、そして新政権発足に伴う暗号資産政策への期待という4つの軸で、10月の重要トピックをまとめました。本レポートは、企業の経営層、事業開発部門、Web3・デジタル戦略部門の方々に向けて、日本のブロックチェーン市場における戦略的な意思決定に役立つ情報を提供します。
エグゼクティブサマリー
2025年10月、日本のブロックチェーン業界で注目すべき動きが相次いだ。JPYCによる国内初の円建てステーブルコイン正式発行、メガバンク3行による共同ステーブルコイン計画の報道、PayPayとBinance Japanの戦略的提携。これらの動きは、長年にわたり整備されてきた規制環境のもとで、ブロックチェーン技術を活用したサービスが、いよいよ実装段階へと移行し始めていることを示している。
さらに、高市早苗首相と片山さつき財務相という新政権の誕生により、暗号資産領域における税制改革や規制整備への期待も高まっている。決済、金融、政治の各分野で起きているこれらの変化を、10月の主要トピックとして整理する。
目次
-
- ステーブルコインの進展──二つのアプローチ
-
- 決済×暗号資産の融合──PayPay × Binance Japan
-
- 金融インフラの進化──RWAとトークン化資産
-
- 政治の動向──新政権と暗号資産への期待
-
- 規制環境のアップデート
-
- 10月のまとめ
1. ステーブルコインの進展──二つのアプローチ
10月、日本のステーブルコイン市場で対照的な動きが見られた。JPYCは個人・小規模事業者向けに資金移動業型のステーブルコインを正式発行し、一方でメガバンク3行は大企業向けに信託型ステーブルコインの共同発行を計画する。この二つのアプローチは、日本のステーブルコイン市場が、リテールと法人の両方をカバーする経済圏へと進化していく可能性を示している。
JPYC:リテール市場への本格参入
10月27日、JPYCが国内初の円建てステーブルコインを正式にローンチした〔日経新聞 2025-10-27〕。
従来のJPYCとの違い
JPYCは2020年から「前払式支払手段」としてステーブルコインを提供してきた。前払式支払手段とは、SuicaやPayPayのように事前にお金をチャージして使う決済手段で、基本的に償還(払い戻し)ができない。
今回の正式ローンチでは資金移動業(第二種)のライセンスを取得し、「電子決済手段」としての位置づけを得た。電子決済手段は改正資金決済法(2023年6月施行)で新たに定義されたカテゴリーで、ブロックチェーン上で発行され、かつ「1コイン = 1円」で償還が保証されるステーブルコインが該当する。
これにより:
- いつでも日本円に償還可能に(前払式では原則不可)
- 発行・償還上限は100万円/回、100万円/日(JPYC EXでの制限。第二種資金移動業の制約)
- 保有・送金額の上限はなし
- 法人決済・クロスボーダー送金への活用が可能に
JPYC EXとは? JPYCの発行・償還手続きを行うための公式プラットフォーム。ノンカストディ型(顧客資産を預からず、顧客自身がウォレットで管理する方式)で運営され、マイナンバーカードによる本人確認を経て、銀行振込で日本円を入金することでJPYCが発行される。発行されたJPYCは即座に登録済みのウォレットに送付され、24時間365日の送金・決済に利用できる。
何ができるようになったのか?
- 1JPYC = 1円の価値連動: 価格変動リスクがなく、決済手段として実用的
- パブリックチェーン対応: Ethereum、Polygon、Avalancheネットワークで利用可能
- 24時間365日稼働: 銀行の営業時間に縛られない送金
- 裏付け資産の保全: 発行額と同額の日本円(預金・国債)を保有
第二種資金移動業のライセンスで運営されるため、発行・償還には上限があるが、個人決済やスモールビジネス向けにフォーカスした設計だ。
ただし、日本ではPayPayなど便利で安心な個人間送金手段がすでに確立されている。そのため、ステーブルコインへの関心は個人間決済よりも、企業間決済の文脈で高まっている。24時間365日の即時決済、国境を越えた低コスト送金、スマートコントラクトとの統合といった特性は、B2B取引で真価を発揮するとも言える。現状の第二種資金移動業における発行・償還上限(100万円/回、100万円/日)は、個人決済や中小企業の日常取引には十分だが、大規模な企業間取引にはより大きな上限枠を持つ第一種資金移動業や信託型の発行が求められるだろう。
JPYC正式発行から24時間での発行量は、対応する3チェーン(Ethereum、Polygon、Avalanche)の合計で約3,700万円にとどまっている〔サードパーティダッシュボード参照、JPYC Analytics 2025-10-28〕。機関投資家や大企業の参入が進んでいないことがこの要因の一つと考えられるが、今後の発展に注目したい。
メガバンク3行:法人決済の標準化へ
一方、10月17日には三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクが、円建てステーブルコインを共同発行する計画が報じられた〔日経新聞 2025-10-17〕。
JPYCとの違いは?
- 信託型発行: 銀行のライセンスを活用し、資産保護を強化
- 法人間決済に特化: 送金上限なし、企業の大口取引に対応
- 相互運用性重視: 3行共通の規格で、銀行間の垣根を超えた決済が可能
- 初期ユースケース: 三菱商事の社内〔日経新聞 2025-10-17〕・社外決済で実証
信託型と電子決済手段型の違い
ここで、日本の改正資金決済法で制定されたステーブルコインの発行形態の種類について整理しよう。以下に分類される:
- 電子決済手段型(例:JPYC): 資金移動業者が発行。発行・償還上限あり(第二種は100万円/回、100万円/日)、個人・中小企業向け
- 信託型(例:メガバンク3行): 信託会社・銀行が発行。送金上限なし、大企業・機関投資家向け
信託型は信託法に基づく資産保全が適用され、発行体が破綻しても利用者資産が保護される点で、より強固な安全性を持つ。一方、電子決済手段型は小口決済に適しており、参入障壁が低い。
ただし、信託型にも課題がある。銀行が信託型ステーブルコインを導入する場合、トークン発行額分の資金を信託銀行が組成する信託に預託する必要があり、この資金は銀行のバランスシートから隔離される。これによるバランスシートからの資金流出・資金効率などの低下が検討事項となる。また、日本では信託型ステーブルコインの裏付資産運用が厳格に制限されており、海外のUSDCのように裏付資産が短期国債などで運用され、その収益が発行企業の収益基盤となっているのと比べると、日本の法規制では不利な条件での競争となる可能性がある〔ABeam Consulting 2024〕。
合計30万社を超える法人顧客を抱える3メガバンクが共通基盤を作ることで、企業決済の新しい選択肢が誕生する可能性がある。海外送金手数料の大幅削減や、サプライチェーン全体での決済効率化が期待される。
棲み分けの構図:
- JPYC → 個人・小規模事業者向け(発行・償還上限100万円/回、100万円/日)
- メガバンク → 大企業・機関投資家向け(上限なし)
この二層構造により、日本のステーブルコイン市場は、リテールと法人の両方をカバーする経済圏へと進化していくことが考えられる。
米国との比較:GENIUS法とステーブルコイン規制
日本のステーブルコイン規制をより詳しく理解するには、米国法との比較が有益だ。
米国のGENIUS法(2025年7月成立)
トランプ大統領が2025年7月18日に署名し、成立した「GENIUS法(Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act)」は、米国初の包括的なステーブルコイン規制法だ〔SBI金融経済研究所 2025-08-25〕。
主な内容:
- 認可制度: 銀行または規制当局の認可を受けた事業者のみが発行可能
- 裏付資産の義務化: 発行額と同等の米ドル、米国債などの準備資産保有が必須
- 二段階の監督体制: 100億ドル以上は連邦機関、それ以下は州当局の管轄
- アルゴリズム型の禁止: 2022年のTerraUSD暴落を踏まえた措置
- 外国発行者への対応: 米国と同等の規制下にある国の発行者のみ参入可能
ドル覇権維持の戦略
GENIUS法の背後には、ドル建てステーブルコインを世界に普及させることで、基軸通貨としてのドルの地位を維持する狙いがある。ステーブルコインの時価総額は2025年5月末で2,300億ドル程度に達しており、USDTとUSDCという2つのステーブルコインが大半を占める寡占市場となっている。BIS(Bank for International Settlements)の報告によると、2024年のステーブルコインによる米国短期国債の購入額は393億ドルと、JPモルガンGMMFの534億ドル、中国の437億ドルに次いで第3番目の買い手だった〔野村総合研究所 2025-06-27〕。
2025年6月、ウォール・ストリート・ジャーナルは、ウォルマートやアマゾンなど米小売大手が独自のステーブルコイン発行を検討していると報じた。クレジットカード決済の手数料削減(年間数十億ドル規模)と決済の即時化が狙いで、GENIUS法の成立を見越した動きとなっている〔Wall Street Journal 2025-06〕。
日本との主な違い
| 項目 | 日本 | 米国(GENIUS法) |
|---|---|---|
| 発行者の要件 | 銀行、資金移動業者、信託会社 | 銀行、連邦/州認可の非銀行事業者 |
| 裏付資産 | 法定通貨、国債など安全資産 | 同左 |
| 送金上限 | 第二種資金移動業は100万円/回 | 100億ドル未満は州規制を選択可能、100億ドル以上は連邦規制へ移行(360日以内)、500億ドル以上は監査済み年次財務諸表の提出義務〔Congress.gov 2025〕 |
| 規制の成熟度 | 世界で最も早く法整備完了 | 2025年に初の包括法が成立 |
日本は2023年6月の段階で世界に先駆けてステーブルコイン規制を整備したが、実際のサービス開始は米国より遅れた。これは主に、規制施行後の事業者ライセンス取得プロセスに時間を要したためだ。電子決済手段等取引業者のライセンス取得には、セキュリティトークンの前例から約1年が必要と見込まれていた〔Progmat 2023〕。
セキュリティトークンとは? 株式や債券などの有価証券をブロックチェーン技術でデジタル化したもの。有価証券である以上、金融商品取引法の規制対象となり、投資家保護の枠組みの中で発行・取引が行われる。価格の安定性を持つステーブルコインとは異なり、保有することで利益分配を受けられる投資商品としての性質を持つ。
一方、米国はGENIUS法により大規模な市場形成が期待される。日本法の特徴は、ステーブルコインを既存の金融システム(銀行・信託・資金移動業)の枠組みに組み込んだ点にある。これは安定性を重視した設計だが、結果として新規参入のハードルが高く、金融機関以外の事業者による革新的なサービス創出が限定される。米国では銀行以外の認可事業者も発行可能で、ウォルマートやアマゾンなど小売大手による参入も検討されている〔Wall Street Journal 2025-06〕。日本が国際競争力を保つには、金融の安定性と新規参入の促進をいかにバランスさせるかが鍵となる。
2. 決済×暗号資産の融合──PayPay × Binance Japan
10月9日、PayPayがBinance Japanの株式40%を取得し、戦略的提携を発表した〔CoinPost 2025-10-09〕。
提携の狙い(公式発表より)
Binance Japan代表取締役の千野剛司氏は、今回の提携について「PayPayの圧倒的なユーザースケールとBinanceの革新的なテクノロジーを融合することで、日本全国のより多くの皆さまにブロックチェーン技術をより身近なものとし、安心で便利な暗号資産サービスを提供できると確信しています」とコメントしている。
PayPay執行役員の柳瀬将良氏は「世界最大規模の暗号資産取引所サービス事業者であるBinanceの日本法人Binance Japanへの出資により、Binanceを利用するユーザーにPayPayの利便性と安全性を備えたソリューションを提供します」と述べた。
具体的な連携施策(検討中)
- Binance Japanアプリでの「PayPayマネー」による暗号資産購入
- 暗号資産売却時の出金先として「PayPayマネー」を選択可能に
提携の意義
従来、暗号資産を購入するには「銀行口座 → 取引所」という手順が必要だった。今回の提携により、PayPayマネーで直接暗号資産を購入し、売却代金をPayPayに出金できる。これは、7,000万人のPayPayユーザーにとって、暗号資産へのアクセスが容易になることを意味する。
業界メディアでは「オン/オフランプ(法定通貨と暗号資産の出入口)の簡素化」という観点から、新規層の参入促進が期待されている。実際、LINE BITMAX(LINEヤフーグループの暗号資産取引サービス)は2023年7月にPayPayマネー連携サービスを2023年7月から開始しており、同年7月〜2024年8月の約1年間で、暗号資産購入件数の約30%がPayPayマネー経由、前年同期比で購入件数が205%増、購入金額が295%増という実績を報告している〔LINE BITMAX プレスリリース 2024-09〕。決済手段との統合が市場拡大につながる事例として注目される。
今後の展望:
- 現在: PayPayマネーでの暗号資産購入・出金機能
- 将来: ブロックチェーン決済やPayPay上での暗号資産保有など、更なる統合の可能性
この提携は、Binanceにとっても日本市場での存在感を大きく高める一手となる。規制の厳しい日本で、決済大手との連携により信頼性を担保できることは大きい。
3. 金融インフラの進化──RWAとトークン化資産
Startale × SBI:次世代取引基盤の構築
8月22日、Startale GroupとSBIホールディングスは、トークン化資産(RWA)の取引基盤を共同開発するための合弁会社設立を発表した〔Startale公式発表 2025-08-22〕。
RWA(Real World Assets)とは? 不動産、株式、債券など、現実世界の資産をブロックチェーン上でトークン化したもの。従来は流動性が低かった資産でも24時間365日取引可能にし、小口化による投資機会の拡大が実現する。
この提携の意義:
- 24時間取引: 証券市場の営業時間に縛られない
- 低コスト決済: 国際送金のコスト削減
- 機関投資家対応: SBIの11兆円の運用資産と6,500万顧客基盤を活用
- グローバル対応: Robinhood、Kraken、Geminiなど海外勢に対抗できる日本発プラットフォーム
RWA市場は2033年までに18.9兆米ドル(約2,800兆円)に達すると予測されており、この巨大市場に向けてStartaleの技術力とSBIの金融エコシステムが融合する。
大和証券の暗号資産担保ローン
10月1日、大和証券は全国の本支店で、グループ会社Fintertechが提供する暗号資産(ビットコイン・イーサリアム)担保ローン「デジタルアセット担保ローン」の紹介を開始した〔大和証券プレスリリース 2025-10-01〕。
現在の税制が生む課題への対応
このサービスの本質は、日本の暗号資産税制が抱える問題への実用的な解決策だ。現行の税制では、暗号資産の売却益は雑所得として総合課税(最大55%)の対象となる。このため、含み益が出ていても売却すると多額の税金が発生し、長期保有を望む投資家にとって「利確できない」というジレンマが生じている。
デジタルアセット担保ローンは、保有する暗号資産を売却せずに日本円の流動性を得られる手段を提供する。これにより:
- 含み益を実現せずに資金調達: 税負担を回避しながら流動性確保
- 長期投資戦略の維持: ビットコインやイーサリアムの長期ポジションを保持したまま資金調達することが可能
- 税制改正までのブリッジ: 分離課税導入まで利益確定を先延ばしできる
サービス概要:
- 融資額: 500万円〜最大5億円(個人向け・不動産購入者向け)
- 担保掛目: 50%(ビットコイン・イーサリアム)
- 金利: 年4.0%〜8.0%(融資額が大きいほど低金利)
- 契約期間: 1年(延長可能)
- 返済方式: 元利一括返済(月々の支払い不要)
4. 政治の動向──新政権と暗号資産への期待
高市早苗首相の就任(10月21日)
高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に就任。日本初の女性首相となった。高市政権は「責任ある積極財政」を掲げ、経済成長を最優先課題に据えている。
技術政策への姿勢
高市氏は経済安全保障担当相としてデジタル社会推進やクールジャパンを所掌し、技術革新への理解を示してきた。2022年のデジタル社会推進本部資料では「ブロックチェーンを基盤とするNFTやDAOの利用促進に向けた環境整備」を方針として明記〔デジタル社会推進本部 2022-10〕。
また、公式サイトで国力を「防衛・外交・経済・人材・技術・情報」の六要素と定義し、先端技術の社会実装と勝ち筋分野への戦略的支援による「成長投資」の必要性を掲げる〔高市早苗公式サイト〕。
一方でサイバー犯罪対策にも積極的で、2025年3月には治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会長として、暗号資産交換業者を含む金融機関の不正取引情報を共有する枠組み創設を提言。イノベーション促進と投資家保護の両立を重視する姿勢がうかがえる。
暗号資産業界への影響:
- デジタル経済の推進: ブロックチェーン・NFT・メタバースなど次世代技術への関心
- 日本維新の会との連立: 規制緩和や新産業育成への期待
- 国家戦略の継続: 岸田政権から引き継がれたブロックチェーン国家戦略の方向性
片山さつき財務相の就任(10月21日)
元大蔵省主計官で金融政策に精通する片山氏が財務相に就任。自民党金融調査会長を4期連続で務めた実績があり、金融業界からの期待が高い。
暗号資産政策への深い関与
片山氏は長年にわたり財務省で多くの重要なポストを歴任し、1988年の証券取引法改正(インサイダー取引規制)や1990年代後半の不良債権問題に対する貸付債権の流動化スキーム導入に関与してきた。
ステーブルコイン規制の立役者
2022年に自民党金融調査会長として資金決済法改正案を了承し、これが現在のステーブルコイン規制の基盤となった。この改正案は2023年6月1日に施行され、ステーブルコインを「電子決済手段」として定義し、法定通貨に価値を連動させたデジタル通貨の国内発行・流通を可能にした。
税制改革への取り組み
片山氏は暗号資産のキャピタルゲイン税の見直しを一貫して主張してきた。現行の税制では暗号資産の売却益は雑所得として総合課税(最大55%)の対象となるが、株式と同様の申告分離課税(20%)への移行を求めている。
2024年12月、片山氏が会長を務める自民党金融調査会とデジタル社会推進本部は、暗号資産を申告分離課税の対象とすることや、暗号資産の一部を金融商品として法的に位置付ける規制の枠組みの見直しについて、加藤勝信金融担当大臣(当時)に緊急提言を行った〔自民党 2024-12〕。
WebX 2025での発言
2025年8月25日〜26日に開催されたWebX 2025において、片山氏は「暗号資産の金商法移行 日本の法整備徹底解説」セッションに登壇〔CoinPost 2025-08-25〕。暗号資産を投資商品として位置づけ、投資家保護を強化するための法改正について議論した。日本の暗号資産市場発展に向けた税制改革の重要性を改めて強調している。
期待される政策:
- 暗号資産の20%分離課税: 現行の総合課税(最大55%)から分離課税への移行を一貫して主張
- 金商法移行の推進: 暗号資産の一部を金融商品として法的に位置付ける枠組み整備
平将明氏のweb3推進要職就任(10月29日)
10月29日、自民党の平将明議員は自身のXアカウントを通じて、党の国家サイバーセキュリティ戦略本部長、デジタル社会推進本部本部長代行、そしてAI・web3小委員会の委員長に就任したことを発表した〔CoinDesk JAPAN 2025-10-29〕。
11月17日追記:金商法改正の動き
11月17日、ブロックチェーン推進議員連盟の第31回会合にて、暗号資産を金融商品取引法の規制対象として位置づける法整備が、2026年の通常国会での実現を目指して検討されていることが公表された。会合で平将明議員は、税制について「いよいよ最終局面となっており、総仕上げとなる」と開会の挨拶で述べた〔CoinPost 2025-11-17〕。
web3政策の中心的存在
石破前内閣でデジタル大臣を務めた平氏は、これまで自民党の「web3プロジェクトチーム」の座長として、 web3分野の政策立案を主導してきた。特に、web3の社会実装や活用を促進し、暗号資産税制に関するホワイトペーパーの取りまとめで中心的な役割を果たした実績がある。
今回の新役職就任により、平氏は高市内閣においてサイバーセキュリティの強化からAI、web3といった先端技術の社会実装まで、日本のデジタル戦略の根幹を担うこととなる。
高市首相、片山財務相、平web3小委員会委員長という三者の体制により、暗号資産・web3分野における政策推進の基盤が整った形だ。これまでの実績を踏まえ、ブロックチェーン業界からは今後のさらなる政策推進に期待が寄せられている。
5. 規制環境のアップデート
10月は暗号資産関連の政策面でも重要な動きがあった。
インサイダー取引の明示禁止
金融庁が暗号資産のインサイダー取引を金融商品取引法で規制する方針を固めたことが報じられた〔日経新聞 2025-10-15〕。未公開情報をもとにした売買を禁止する規定を金商法に明記し、違反者には課徴金を課す。2026年の通常国会に改正案を提出する方針で、証券取引等監視委員会による犯則調査の対象とし、疑わしい取引があれば課徴金勧告や刑事告発につなげられるようにする。これにより、暗号資産が「金融商品」として位置付けられ、投資家保護が強化される。
銀行グループの暗号資産取引サービス容認
金融庁が、銀行グループによる暗号資産取引サービスを容認する方向で検討〔日経新聞 2025-10-21〕。これにより、メガバンクが子会社を通じて取引所を運営したり、カストディサービスを提供したりすることが可能になる。
6. 10月のまとめ
10月の動きを俯瞰すると、3つの大きな潮流が見えてくる。
① 決済インフラのブロックチェーン化
- JPYCとメガバンクのステーブルコインが、個人と法人の両方をカバー
- PayPayとBinanceの連携により、暗号資産と日常決済の接点が拡大
- 24時間365日、国境を超えた低コスト決済の実現へ
② 金融資産のトークン化の進展
- StartaleとSBIのRWA取引基盤により、株式・不動産などがオンチェーン化
- 大和証券の担保ローンにより、暗号資産の資産クラスが誕生
- 機関投資家の参入準備が進行
③ 政策・規制の整備継続
- 高市首相と片山財務相による新政権が、経済成長を重視
- 平将明氏のWeb3推進要職就任により、政策実行体制が強化
- 20%分離課税やインサイダー規制など、投資環境の整備が進行
- 銀行グループの参入容認により、伝統金融と暗号資産の融合が加速
今後の展望
2025年10月は、日本の暗号資産市場において具体的なサービスが動き出した月として記録されるだろう。規制が整備され、大手金融機関が参入し、政治的な環境も整いつつある。
PayPayとBinance Japanの連携を皮切りに、同じような顧客基盤と暗号資産サービスを持つ企業(楽天の楽天ウォレットやメルカリのメルコイン)なども、既存ユーザーへの暗号資産サービス展開へむけての動きを加速することが期待される。JPYCや3メガバンクのステーブルコインが、個人・法人のどちらの領域でどのように浸透していくかも注目だ。
何より、高市首相と片山財務相、そして平将明氏という、暗号資産・web3分野に深い理解を持つリーダーシップ体制が整った。これから税制改革や金商法改正といった政策環境の整備が進んでいくことが期待される。日本のブロックチェーン業界は、規制対応を経て実装のフェーズへと移行しつつあり、Startaleもその最前線で、RWA取引基盤の構築をはじめとした技術開発とビジネス実装を加速させていく。この歴史的な転換期において、業界全体が協力しながらイノベーションを推進し、日本のブロックチェーンの未来を創造していく。
参考文献・出典一覧
主要メディア
- Wall Street Journal「Walmart and Amazon Are Exploring Issuing Their Own Stablecoins」(2025-6-13)
- 日経新聞「ステーブルコインJPYC初日、3時間で1500万円発行」(2025-10-27)
- 日経新聞「3メガバンク、ステーブルコイン共同発行へ」(2025-10-17)
- 日経新聞「銀行グループの暗号資産取引サービス容認へ」(2025-10-21)
- 日経新聞「金融庁、仮想通貨のインサイダー取引規制を導入へ」(2025-10-15)
業界メディア・取引所
- CoinPost「PayPay、Binance Japanへ40%出資 戦略的提携を発表」(2025-10-09)
- CoinPost「片山さつき氏、財務大臣に起用 暗号資産規制整備にも期待」(2025-10-21)
- CoinPost「片山さつき氏らが語る暗号資産の金商法移行(WebX 2025)」(2025-08-25)
- CoinTelegraph「高市氏が首相就任なら仮想通貨政策に新風」(2025-10-21)
- CoinDesk JAPAN「前デジタル大臣・平将明氏、高市内閣でWeb3推進の要職に就任」(2025-10-29)
- JPYC Info (2025-10-28)
- CoinPost「暗号資産の金商法移行が本格化、分離課税実現へ最終局面=ブロックチェーン議連」 (2025-11-17)
企業公式発表
- Progmat「改正資金決済法の施行を受けて~ステーブルコイン入門~」(2023)
- Startale Group「SBIホールディングスとの合弁会社設立について」(2025-08-22)
- Fintertechプレスリリース「Fintertechの暗号資産担保ローン紹介開始」(2025-10-01)
- Fintertech公式サイト「デジタルアセット担保ローン」
- LINE Yahoo プレスリリース「PayPayマネー連携サービス実績報告」(2024-09)
研究機関・シンクタンク
- ABeam Consulting「実現フェーズに入ったデジタル通貨~ステーブルコイン・トークン化預金の相違点・導入時の検討ポイント~」(2024)
- 野村総合研究所「ステーブルコインと米国のドル覇権」(2025-06-27)
- SBI金融経済研究所「GENIUS法の詳細解説」(2025-08-25)
政府機関・政党
- Congress.gov「Stablecoin Legislation: An Overview of S. 1582, GENIUS Act of 2025」(2025)
- 金融庁「暗号資産・電子決済手段の移転に係る通知義務(トラベルルール)」(2023-06-01)
- デジタル社会推進本部「ブロックチェーン技術を基盤とするNFTやDAOの利用等の推進」(2022-10)
- 自民党「暗号資産を国民経済に資する資産へ 緊急提言」(2024-12)
- 高市早苗公式サイト「基本理念」
次回レポートは2025年12月下旬公開予定
本レポートは2025年10月31日時点の情報に基づいています。市場環境や規制は変化する可能性があります。